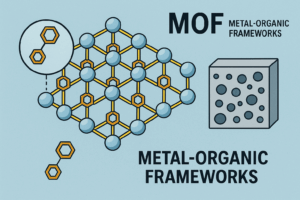「人口減少時代を生きるシンポジウム〜新境地へー水循環日本への扉を開く〜」(主催 一般社団法人水の安全保障戦略機構 2025年5月30日@奥村組クロスイノベーションセンター+オンライン配信)報告記事
― 静かに進行する水インフラの危機と、私たちにできること
ある日突然、水道が止まる──そんな日が本当に来るとしたら、あなたはどうしますか?
私たちは日々、料理や洗濯、トイレ、シャワーに至るまで、水道の恩恵を「当たり前」として享受しています。しかし、そうした生活を支える上下水道インフラは、いま静かに、そして確実に限界を迎えようとしています。
2025年5月30日、東京で開催されたシンポジウムでは、この“上下水道クライシス”に警鐘を鳴らす専門家や自治体関係者が集まり、課題と解決策を具体的に提示しました。本記事では、研究者や自治体関係者の発表をもとに、以下の3つの視点から「水と暮らしの未来」を考えます。
水の危機を知るだけでなく、課題にどう立ち向かうか。地域の実践にヒントがあります。
※本記事は、SDGsの以下の目標と深く関わっています:
▶︎目標6「安全な水とトイレを世界中に」
▶︎目標11「住み続けられるまちづくりを」

「水が出るのは当たり前」じゃなくなる未来 (話題提供:橋本淳司氏)
― 水道クライシスにどう備える?
「水道は、昭和の時代に完成した成功体験。でも令和の水道は、持続可能性を問い直す時代です」
そう語るのは、水ジャーナリストで武蔵野大学客員教授の橋本淳司氏。シンポジウムの冒頭で、橋本氏は日本の水インフラが直面する危機的状況を明らかにしました。
全国で年間約2万件の漏水事故、2000件を超える道路陥没――老朽化した水道管が原因の事故が、もはや日常になりつつあります。一方で、人口減少と節水の普及により使用者が減少し、水道事業の収入も激減。更新に必要な費用は増えるのに、使う人は減っていくというジレンマに直面しています。
「このままでは、水道管の更新完了に150年かかる地域もある」と橋本氏。持続可能な制度設計への転換が急務です。
つまり、私たちの街の水道管がいつ壊れてしまってもおかしくない状況にあるのに、新しい水道管に替えるのに最大150年も待たなければならないという危機的状況にあるということです。
当たり前」を見直すところから始めよう (スピーカー:吉岡律司氏)
― 矢巾町の水道改革は“自分ごと”から始まった
このような水道の危機的状況を打破するために、岩手県矢巾町(やはばちょう)では、水道を「見えない存在」から「住民とともに考えるテーマ」へと変える取り組みが始められました。きっかけは、今後の人口減少を見据えたとき持続可能な水道事業の運営体制の維持が困難であるという危機感でした。
上下水道課長・吉岡律司氏は、「当たり前にある水道に、住民の関心と納得が加わったとき、水道事業の持続可能な仕組みに一歩近づける」と語ります。
吉岡氏が取り組んだのは、水道ビジョンを住民と町が共に作り上げる「共創」でした。そして、ショッピングセンターでのアンケート、住民サポーターによるワークショップなど、地域住民が“自分ごと”として参加できる機会を数多く設けました。
こうした吉岡氏の取り組みの結果、町民との間に「信頼・知識・道徳意識」という協力の土壌が育まれました。特に、町民954人から得られた「水は安く、安全で、美味しくあってほしい」といった率直な声は、水道制度の見直しや料金改定の際に、根拠あるデータとして活用されました。その結果、町民との対話を通じて政策への理解と納得を得ることができ、単なる制度変更ではなく、共に未来を築くプロセスが現在進行中です。
危機のど真ん中で選んだ“攻めの水道改革” (スピーカー:清野馨氏)
― 石狩市・清野氏が実践した「再生の5ステップ」
2000年代初頭、北海道石狩市では、漏水や断水が相次ぎ、水道事業は文字通りの“クライシス状態にありました。この危機の現場で指揮をとっていたのが、当時の水道担当部長・清野馨氏です。「私たちの仕事は、“壊れる前に直す”こと。けれど、それを理解してもらうには、暮らしの現実とつなげて伝える必要があるんです」(清野氏)
「毎週のように道路が陥没し、住民の暮らしが脅かされていた」と語る清野氏は、技術者としての視点と経営の目線を融合させた“5つの戦略”を打ち立てました。
石狩市がとった5つの実践策
1.まず「自分のまちを知る」ことから:アセットマネジメント(資産管理)を徹底し、劣化や費用の全体像を数値で把握。
2.優先順位をつける:すべてを同時に直すのではなく、「どこから着手するか」を合理的に整理。
3.根拠ある“先延ばし”:予算が限られる中でも、緊急性と耐久性を見極め、最適なタイミングで更新。
4.サイズダウンとコスト設計:将来人口を見据えて、水道管の太さや素材を見直し、“過剰スペック”を回避。
5.料金改定で財源確保:段階的な値上げ(17%)を説明し、合意形成を図った。
この取り組みによって、年間7億円必要だった更新費用を、3.2億円まで圧縮。
しかも、「質を落とさず、コストだけ下げる」ことを実現しました。
信頼と合意形成のカギは「説明の質」
とはいえ、財源の確保には避けて通れない“料金改定”の壁が立ちはだかりました。
清野氏は、町内会ごとに足を運び、繰り返し説明を続けました。
議会では、深夜1時まで12時間にわたる議論の末に、ついに値上げが可決。
「一方的な押し付けでなく、リスクも数字も見せる“リスクコミュニケーション”が合意の鍵だった」と振り返ります。
その結果、石狩市の水道は、住民理解の下、持続可能な水道事業として歩んでいます。
“正直戦略”と“広域連携”が水道を救う (トークセッション/モデレーター:中村晋一郎氏、コメンテーター:青山アリア氏)
―現場から生まれるリアルなイノベーション
「正しいことを、正直に伝える。それが最大のイノベーション」
そう語る清野氏の言葉に、会場は静かにうなずきました。住民との“正直な対話”による信頼構築、そして運営連携による隣接自治体の“水平統合”は、限られた人材や財源の中で、今すぐできる現実的な改革です。
コメンテーターの青山アリア氏(株式会社CB最高執行責任者)は、「水道料金の請求書は、いわば“ラブレター”」と語りました。単なる支払いの案内ではなく、水がどれほど大切な存在であり、それを誰が、どのようなしくみで私たちのもとへ届けているのか――そうした「水の裏側」にある物語を伝える手紙にもできる、というわけです。普段は気に留めない1枚の紙が、暮らしとインフラをつなぎ直す大切なコミュニケーションになるかもしれません。
今日から私たちができる3つのこと(編集後記)
―「水のある日常」を次世代につなぐために
では、私たち一人ひとりには何ができるのでしょうか?発表内容をもとに、今日からできる3つの行動をご紹介します。
1.自治体の議論に「無関心でいない」こと
水道の料金改定や統廃合は住民の意見によって大きく左右されます。まずは、説明会やパブリックコメントに関心を。
「決まったあとで“知らなかった”では遅い。関わる意思表示を、今こそ」(清野氏)
2.水の「使い方」と「支え方」を見直す
節水はもちろん、料金制度や受益者負担への理解も大切です。
「自分の地域だけ安ければいい」では、全体が立ち行かなくなることも。連接自治体が水道事業の運営を連携して行う『 「共通負担」という発想が、過疎地域を守り、都市部にも跳ね返ってくる利益になります』(清野氏)
3.学校や地域で「水の話」をする
日常の中で、水のありがたさとその裏側を共有することが、未来の担い手を育てます。
「暮らしの中で“水が届くありがたさ”を語り継ぐことが、次の世代の防災にもつながります」(吉岡氏)
上下水道の未来は、行政や技術者だけに任せられるものではありません。
私たちの関心と行動が、あたりまえに蛇口をひねれる未来を守るカギになるのです。
==================================================
登壇者
水ジャーナリスト、武蔵野大学客員教授 橋本淳司氏
モデレーター:名古屋大学大学院工学研究科 准教授 中村晋一郎氏
スピーカー:元・石狩市建設水道部水道担当部長(水道技術管理者) 清野馨氏
スピーカー:岩手県矢巾町上下水道課長 吉岡律司氏
コメンテーター:株式会社CB 最高執行責任者 青山アリア氏
==================================================
シンポジウムの開催概要:https://www.waterforum.jp/news/23105/
【関連記事】
◆持続可能な国際スポーツ大会のさらなる進化を目指して──VNL2025 千葉大会の挑戦
https://japan-sdgs.or.jp/news/6114.html
◆スポーツエンターテインメントとSDGsを融合する、バレーボールネーションズリーグの素晴らしさ
https://japan-sdgs.or.jp/column/6021.html
◆<AIポッドキャスト>【SDGs JAPAN PORTAL】「持続可能な国際スポーツ大会のさらなる進化を目指して──VNL2025千葉大会の挑戦」を、YouTubeにアップしました。AIのトークによるポッドキャストで、VNL2025千葉大会の素晴らしさを、音声でダイレクトに感じられる番組となっています。ぜひご視聴ください。
https://youtu.be/xm_V6FdmeNc?feature=shared