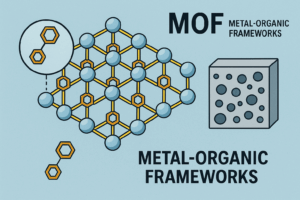理事改選で体制刷新も、国際担当の業務執行理事の続投に疑問の声。一方で、見識を示した評議員会に高い評価
8月3日に閉幕した「バレーボールネーションズリーグ(VNL)」。日本代表女子は3位決定戦に敗れて2大会連続のメダル獲得を逃し、男子も準々決勝で敗退して3大会連続のメダル獲得はならなかったが、千葉大会での躍動は日本中を沸かせ、2028年ロサンゼルス五輪に向け明るい希望を持たせた。しかし、活況に沸く日本バレーボール協会(JVA)が今、スポーツの国際化に“逆行”するミスで揺れている。
6月下旬に行われたJVAの理事改選、会長や副会長、業務執行理事の選定。2年に一度の恒例行事だが、改選直前に帰化に絡む「所属国協会(FoO)変更手続き問題」が明らかになり、ガバナンスやコンプライアンスが問われる事態となった。
発端は2024年3月5日、国内リーグで活躍していた女子選手側からJVAにあった帰化の進展の問い合わせだった。
話はその約2年前にさかのぼる。JVAによると2022年6月24日、母国で代表歴のある女子選手の所属チームから、JVAの川合俊一会長に帰化の支援依頼があった。帰化をして日本代表に選出されることを希望した選手は2023年1月23日に帰化を申請。同年2月14日に川合会長と所属チーム担当者が面談し、国際バレーボール連盟(FIVB)が所管する「所属国協会(「Federation of Origin」=FoO)変更手続き」などを支援する活動が始まった。
一方、それまで他国で代表経験があっても所属国・地域の協会の変更をFIVBが認めて2年が経てばその国の代表選手になれ、オリンピックやVNLなど国際大会に出場することが可能だった。
しかし、FIVBは世界トップレベルの選手の“流出”を防ぐため、2023年6月23日の理事会でFoO変更手続きを改訂。過去に代表歴がある選手は、国籍を変更しても所属国協会の変更を認めないと決定し、同年7月5日にホームページ(HP)上で公開した。通常は即日発効するレギュレーション変更だが、90日間の猶予期間後、同年9月21日から施行された。
ところが、JVAがFIVB理事会決定を知ったのは、女子選手側から問い合わせのあった2024年3月5日だった。しかも、FIVBからJVAを代表するFIVB理事(理事会は欠席)に2023年6月14日に資料がメールで事前送付され、JVAにも転送されていたが、資料を共有していた職員らは内容を読み込んでいなかった。さらに、FIVBのHP上の記載を見ても気付かなかったという。JVAによると、帰化申請の動きを組織として共有していなかったことが、見落としの大きな原因だったという。
ミスは誰にでも起こる。だが、バレー関係者が残念がるのは、その後のJVAの対応だ。2024年3月5日に女子選手側からFoO変更手続きの進展の問い合わせを受けた国際担当の内藤拓也業務執行理事は、1か月間、女子選手側と連絡を取らず放置した。
第三者委員会は、この件に関し「(問い合わせを受けた)2024年3月5日以降、JVA全体の組織課題に早い段階からすべきであった」とし「『(JVAの)危機管理規定』に則り、危機管理事態に準ずる対応を取るべきであった」と、内藤業務執行理事の対応の拙さを厳しく指摘した。
内藤業務執行理事は、メール見落としなどのミスは謝罪しつつ「FIVBに問い合わせたが、猶予期間に適応されるのは帰化手続きが済んだ選手が対象。帰化手続き中の選手の例外規定はない」と説明。JVAのミスがなくても、女子選手のFoO変更は認められないという説明に終始した。
一方、國分裕之専務理事は「気付かなかったことは(JVAの)落ち度。タイムリーな把握が出来ておらず反省している」と謝罪し、猶予期間中にFIVBに帰化申請中であることなどの説明をしていれば、FoO変更が認められた可能性について「アクションを起こせていないので、可能性を否定するものではありません」とした。
バレー関係者によると、「90日間の猶予は、国情によって帰化申請手続きの事情が違うため、選手を代表するアスリート委員会が要望したため設けられた」という。
JVA内部にある、國分専務理事と内藤業務執行理事の見解の相違。バレー関係者からは、「猶予期間中に帰化に時間がかかる日本の事情を説明していれば、人権問題に過敏なFIVBが却下することは考えづらい。猶予期間に、日本の事情を反映した特例措置を訴えることができた」「國分専務理事の見解が一般的な考え。可能性も否定する内藤業務執行理事の説明は、責任逃れにしか聞こえない」「選手ファーストの考えに立てば、可能性を否定する立場はとらないだろう」という声が上がっている。
関係者によれば、内藤業務執行理事がメディアに説明するFIVBからの回答は、「FoO変更手続き問題」が報道で表面化してリモート会見を開催するまで約10日間に、FIVBに問い合わせた時のものだったという。第三者委員会の報告によると、内藤業務執行理事は、2024年5月3日と6月20日にFIVBに対しメールを出している。
この間のやり取りは公表されていない。筆者がJVAに公開を求めたところ、JVAは「当事者(FIVB、当該選手双方)との信頼関係維持・構築の観点から、これ以上の具体的な情報をJVA側から発出することはいたしかねます」(広報チーム)として明らかにしなかった。
これについても、バレー関係者は「猶予期間が過ぎた現状では、FIVBはそういう回答をするのは当然では」「人権問題になりかねないので、FIVBは『早く事情を説明してくれれば、考慮したのに』という立場をとってくれたのでは」と指摘する。
内藤業務執行理事は、女子選手のFoO変更について、今後、国際弁護士と相談し五輪憲章を根拠にFIVBに救済措置を訴えていくなどという内容の説明をしている。だが、「五輪憲章を基に交渉を進める手法は、他の関係者から教えてもらったのでは」と冷めた目で見る関係者もいる。
存在感を示した評議員会
今回の「FoO変更手続き問題」で、選手ファーストの立場を貫く國分専務理事と並んで存在感を示したのは、評議員会だ。
理事を選任し、執行部を指導・監督する諮問機関の評議員会。今回の改選にあたり、コンプライアンス委員会の結論が出ていないまま、内藤業務執行理事らが含まれた理事候補の選任の審議を“拒否”し、差し戻した。
さらには、JVAに対し、法令や規則を遵守する管理体制を明確にし、ガバナンス改善を要請する「意見書」も発出した。ガバナンス全体の検証と改善を求め、報告義務も課したものとみられ、こちらも極めて異例の指摘だった。
今回の理事改選では、柳田将洋さん(東京㎇)が現役選手として初めて理事に選ばれるなど、体制を刷新した。ただ、関係者によれば、改選にあたり内藤氏と灰西克博氏の理事再任に、疑問の声も挙がったという。「詳しい事情はわからないが、業務執行理事を務めることになった理事が多くの評議員の賛同を得られていないとすれば、組織にとって極めて不幸なこと。そんな理事が業務執行理事を務めることができるのだろうか」という素朴な疑問を呈する。
「FoO変更手続き問題」で、残念なのは川合俊一会長の対応だ。女子選手が当時所属していたチーム関係者から、帰化について相談を受け支援を約束。本来業務でなかったが、人権問題も絡むためだろう、少数の職員らで対応にあたらせた。第三者委員会の報告では、2023年12月14日のJVA本部長会議の議事録に「帰化対策プロジェクト」の記載があったことから、それ以前から完全な秘密主義で情報を共有していなかったわけではないとみられる。
また、一部で帰化に携わったJVA幹部が、法務当局への上申書を偽造して当時の所属チームに承認を求めたという報道がなされた。関係者によれば、就労実態などによって帰化手続きが進めやすくなるケースがあることから、確認のために書類を作成したもので、「当時の所属チームに女子選手の就労実態などを確認し、誤りがなければサインをしてほしいと求めただけ。文書を偽造したとは言えない」と指摘する。しかし、この幹部はJVAのコンプライアンス委員会からは「事実と異なる文書を作成した」との理由で、ただ一人、処分を受けることになった。
一方、川合会長らは処分を受けず、給与を自主返納すると2025年6月16日に発表したが、返納額や期間について発表しなかった。「世間の相場という言い方は僕はしないですけど、世間のある程度のことを知らずに勝手に会長が決めちゃって、逆のことやったら逆に言われますし、どっちにしたってなんか言われることだと思うんで。とりあえず、どのような感じのことが妥当なのかということは、調べちゃいけないというなら調べませんけども」と川合会長。
組織のトップが責任を感じて自らに“処分”を課す一つのケースが給与の自主返納。“自主”であるなら、川合会長は自ら決めるべき。それがトップとしての責任の取り方ではないだろうか。
選手の人権より、組織を守るのか
一連の「FoO変更手続き問題」を取材して感じるのは、JVAは選手より組織を守っているのではないかという疑念だ。個人を特定される可能性があるため、詳細は紹介できないが、女子選手はオリンピック出場の夢を追い求め、日本代表になって、日本のために活躍を誓い、国籍を変更する大きな決断をしたと聞く。その大きな夢が、JVAの組織的な問題や、国際担当の業務執行理事の不誠実な対応で翻弄され、絶たれようとしている。
スポーツ選手の帰化に賛否はある。しかし、帰化は個人の選択であり非難されるべきものではない。国の行政機関も、国益につながるとして支援を惜しまない。
また、今回の「FoO変更手続き問題」に関し、選手側に全く落ち度がないのに、SNS上で誹謗中傷も相次いだ。リモート会見では、スポーツ紙で長年バレー取材に携わっているベテラン記者から「選手に対する誹謗中傷も結構ありますので、そのあたりも協会でケアしていただけたらと思います」と異例の要望が出された。時間の制限もあったのだろうが、川合会長からは「はい、わかりました」という回答があっただけだった。
「選手の人権を守るのか、組織を守るのか」――。現時点で五輪出場という「夢」を奪われた選手から突き付けられた心からの訴え。問われるべきは、帰化を進めたことでなく、FoO変更手続きを見落としたミスとその後の対応ではないだろうか。JVAには責任逃れではない、真摯な対応が求められている。
取材・文:北野正樹
読売新聞大阪本社を経て、2020年12月からフリーランス。プロ野球・南海、阪急、巨人、阪神のほか、アマチュア野球やバレーボールなどを担当。関西運動記者クラブ会友。
【関連するSDGsのゴール】
10: 人や国の不平等をなくそう
「各国内及び各国間の不平等を是正する」という目標であり、そのターゲットとして、以下の内容が明記されています。
<10.2>
2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。
<10.7>
計画に基づき良く管理された移住政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。
16: 平和と公正をすべての人に
「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する」という目標であり、そのターゲットとして、以下の内容が明記されています。
<16.3>
国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平等なアクセスを提供する。
<16.10>
国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。
※持続可能な開発目標SDGsとは/持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。
出展:外務省(JAPAN SDGs Action Platform)